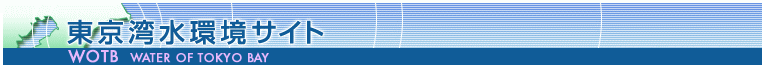|
(1) ����Ɖۑ�
���悩�瓌���p�֗������鉘�����ׂ��팸���邽�߁A�������̐����A�n�掖��ɉ����A
�_�ƏW���r���{�݁A�������������̊e�퐶���r�������{�݂̐����A�͐쒼�ڏ�
�{�݂̐����A�݂͊̉��ǁA�X�т̐����E�ۑS���̐������P���Ƃ����{����Ă����B
�������Ȃ���A�����p�͗���ɑ傫�ȉ�������L�����������̂��߁A�����x�h�{
���ɂ��Ԓ��E�����̌��ۂ��݂���B���̂��߁A�L�@�������팸�Ƌ��ɁA�h�{����
�ł��钂�f�A���̏������ΏۂƂ����������P���Ƃ̍X�Ȃ鐄�i���K�v�ł���B��������
����A���x�����̓����ɂ͐V���Ȕ�p���S�������A���̓����͏\���i��ł��Ȃ��B���
�āA�͐���܂߂������ۑS�A�Ⴆ���x�����ɗv�����p���S�ɂ��ẮA��v�ƕ��S
�̊ϓ_����s���P�ʂ����ł͂Ȃ�����P�ʂł̍œK�ȕ��@�ɂ��Ă��������邱�Ƃ��d
�v�ł���B�܂��A�����p�ɗ������鉘�����ׂɂ́A�ƒ�A���Ə������甭������_����
�ȊO���A�s�X�n�A�_�n�����痬�o����ʌ����ׂ�����A�������P��}�邽�߂ɂ́A��
������i�߂�K�v������B
�ߔN�ł́A���W���[�E���N���G�[�V���������̊������ɂ��A�l�X�̊C�ւ̉�A���i�݁A
�e����݁A�l�H�C�l�̐�������}���Ă���ɂ�������炸�A�J�V�����͕��V�S�~����
���݂��Ă��邽�߁A�i�ρA�q���ʂ̊ϓ_����A���P��}��K�v������B
�@ �������ʋK��
�����p�ɂ����ẮA�b�n�c���̐������̕ۑS�ɌW�鐅��������m�ۂ��邱�Ƃ��
�r�Ƃ��ĊW�n�悩�甭�����鉘�����חʂ𑍍��I���v��I�ɍ팸���邽�߁A�e�s�{
���̑��ʍ팸�v��̍���A���ʋK����ɂ�鎖�Əꓙ�̋K���A�����r����̐��i
������e�Ƃ��鐅�����ʋK�����A���a�T�S�N�x�����{����Ă��Ă���B�����P�U�N�x���
�W�N�x�Ƃ����5 ���������ʋK���ɂ����ẮA����܂ł̂b�n�c�ɉ����V���ɒ��f�y�т�
�팸�̑ΏۂƂ��ꂽ�Ƃ���ł���B
�A ��������
���������Ƃ͕����P�R�N�x���݂P�R�U�s�����ɂ����Ď��{����Ă���A�����p�������
�W�P�ӏ��̉���������i�������扺�����̏�����͂P�V�ӏ��j���ғ����Ă���B�����p����
���̂Q�W�S�V�D�R���l�̏Z���̂����A�Q�S�S�S�D�Q���l�̏Z�����������ɐڑ����Ă���A������
�̏����l�����y���͂W�U���i�S�����ςU�R.�T���j�ƍ����ɂ���B�������A�����s������
���y���́A�܂��\���ƌ������A�����s�����𒆐S�Ƃ������y���i���K�v�ƂȂ�B
�����p�̐��������B�����邽�߂ɁA�����p��ΏۂƂ��闬��ʉ�������������
�v��Ɋւ����{���j�ł͉������̍��x�������K�v�Ƃ���Ă���B�������A�����P�R�N�x
���݁A�����p������̏�����̂������x���������Ă��鏈����͂P�S�ӏ��݂̂ł���A
���x�����l���͂P�V�T�D�V���l�ō��x�����l�����y���͂U���ƂȂ��Ă���A�S�����ςX�D�V���A
�ɐ��p�y�ѐ��˓��C�Ɣ�r���ĒႢ�ɂ���B�����p�̐������P�ɂ͍��x�����̓����͕s���ł���A����A���͂ɐ������i��}��K�v������B
�����p������ɂ����ẮA�����P�R�N�x���݁A�R�V�s�s�����������������̗p���Ă���B
�ߔN�A����������������̉J�V���������������ɂ����ӊC��̐������������݉���
�Ă���A�������������̉��P���ً}�Ɏ��{����K�v������B
�_�ƏW���r�����Ƃ́A�����P�R�N�x���݁A�����p������̍�ʌ��A��t���ɂ����ĂR�O
�s�����Ŏ��{����Ă���A�����p������ɂU�U�ӏ��̔_�ƏW���r���{�݂��ғ����Ă���B
�����p������ł͂R�W�D�T���l�������Ώېl���ƂȂ��Ă���A���̂����T�D�R���l�̏Z����
�_�ƏW���r���{�݂ɐڑ����Ă���A�����Ώۋ��ɑ��鐮�����͂P�S���ƂȂ��Ă���B��
�������̐������́A�S���̕��ϐ������R�P���ɔ�גx��Ă���A����A�����p����ɂ���
��_�ƏW���r���{�݂̐������d�_�I�ɑ��i����K�v������B
�����������������Ƃ́A�����P�R�N�x���݁A�����p������̂P�O�U�s�撬���Ŏ��{
����Ă���B�����p�Ɋւ��S�s���ł́A�P�P�T���l�̏Z���������g�p���Ă���A��
���ɂ�鏈�����͂S���ƂȂ��Ă���B����A���������̌����Ƃ��Ȃ�P�Ə������ɂ�
���ẮA�������������V�ݔp�~�ւ̎�g���s���A�����P�Q�N�x�ɂ͏��@�̉�����
���A���ݒP�Ə��������g�p������̂́A�������\�菈�����ɂ�����̂������A��
���������ւ̐ݒu�ւ����͍\���ύX�ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƂȂ����B����́A
�Z���ӎ������߂�ق��A�s��������̂ƂȂ��ď��̐����E�ێ��Ǘ����s�����Ƃ�ϋ�
�I�Ɋ��p���A�P�Ə��������獇���������ւ̓]���𑣐i����ƂƂ��ɁA���f�܂�
�͂��̏������\��L������̐����𑣐i����K�v������B
�B ���̑�
�X�т́A���ؓ��̐A����y��̓����ɂ��A�����̏ɖ𗧂��Ă���B�܂��A�S�s����
������X�т̖ʐς͂S�V��ha �Ƒ��ʐς̂R�U�����߂Ă���B
���̂��߁A�Ԕ����̕K�v�ȐX�тɑ��A���̏d�_�I�Ȏ��{���A�X�т̐����Ɏ��g�ނ�
�Ƃ��ɁA�X�т̐����Ղł���ђn��ۑS���邽�߂̎{�݂̐�����ۈ��т̎w��ȂǁA
�v��I�ȐX�т̐����E�ۑS�𐄐i���Ă���B
�������Ȃ���A�ыƂ̍̎Z���̈����Ȃǂɂ��A���̌�ɐA�т��ꂸ���u����Ă���X
�т�����ȂǁA�K�v�ȐX�т̐������\���s���Ă��Ȃ��X�т��������邱�ƂȂǂ܂��A�X�т̐����E�ۑS���v��I�Ɏ��{���Ă������Ƃ��K�v�ł���B
(2) ���悩��̉������ׂ̍팸����
�����p�ɂ����鑁�}�Ȑ������P��}�邽�߁A�������ʋK�����x�Ɋ�Â��e�s��������
���鑍�ʍ팸�v��̒����Ȏ��{�y�ю��Ə�ɑ��鑍�ʋK����̏���̓O�ꓙ��}
��ƂƂ��ɁA����P�ʂɂ����āA�W�@�֓��ƘA�g�̂��ƁA���x�����A�ʌ��������ב�
�����܂߂������I�A�����I�ȕ��팸�̂��߂̌v�����y�ю��Ǝ��{��}��B�Ȃ��A��
���I�ȕ��팸�̂��߂̌v�������s�����߁A�J�V�����̗��o���חʂ̕]�����s������
�̒��������{����B
�܂��A���������ΏۂƂ��āA�����I�Ɋ�����̖ڕW��B�����邽�߁A�V���Ɍo
�ϓI��@�̓K�p���܂ޗ���S�̂̔�p���S�̕��@�ɂ��Č�������B
�@ �����Ɍ������{��
�������ɂ����ẮA�����p����ʉ��������������v��Ɋւ����{���j�Ɋ�Â���
�e�s���ɂ����闬��ʉ��������������v�擙�ɏ]���A�����s�����ł̕��y���i�A���x
�����̑��i�A���������������P����ϋɓI�ɍs���B�v����ԓ��ɁA������ʼn���������
��\�肵�Ă���S�s�����ɂ����āA���Ƃɒ��肷����̂Ƃ��A���x�����ɂ��Ă��V����
�T�˂Q�O������ł̋��p�J�n��ڎw���B
����������������̉J�V���������������͕�����ł̐����̈����A�����p�҂ɑ�
��i�ρE���O�q���y�ѐ��Ԍn�ւ̉e�������O����Ă��邱�Ƃ���A�������������̉��P
�v������肵�A�P�O�N�ȓ���ړr�Ɉȉ��̂悤�ȖڕW��B�����邽�߁A�d�_�I�ɉ��P����
�i��߃X�N���[���ݒu�A�����{�݁A���Ŏ{�ݐ������j�����{���Ă����B
���{�����e��
������������������r�o�����a�n�c�������חʂ����������ȉ��ɂ���B
�����R�f����|���v�{�݂ɂ�����S�Ă̓f�����ɂ����ĉz�������Ȃ��Ƃ�����
����B
�������Ƃ��āA���R�f����|���v�{�݂ɂ�����S�Ă̓f�����ɂ����Ě�G���̗��o
�h�~�����{����B
�_�ƏW���r���{�݂̐����Ɋւ��āA�����p����̒n����d�_�I�ɐ�������ƂƂ��ɁA��
���{�݂̋@�\�����A�K�v�ȍ��x�����̑��i��}��B
���ɂ��ẮA�Z���ӎ������߂�ق��A�s��������̂ƂȂ��ď��̐����E�ێ�
�Ǘ����s�����Ƃ�ϋɓI�Ɋ��p���A�����̒P�Ə���������A�����������ւ̓]
���𑣐i����ƂƂ��ɁA���f���͂��̏������\��L������̐����̑��i��}��B
�͐�̏�ɂ��ẮA�͐쒼�ڏ{�݂ɂ��A�p���̓����A���֓�
�̗L�@������ɉ����A���n��͌������Đ��ɔ������f�E��̉h�{���̍팸���A��
�Y�͐�W�Z���̈ӌ����ӂ܂����͐쐮���v��Ɋ�Â��A�ϋɓI�ɐ��i����B
�S�s���̈琬�тP�X��ha�ɂ����āA�������ɂ������邽�߁A�K�ȊԔ��̎��{�A��
�w�т̑����ȂǑ��l�ȐX�т̐�����i�ߎ��̌��S�Ȑ����≺�w�A���̔ɖ𑣂��Ƃ�
���ɁA�ђn��ۑS���邽�߂̎{�݂̐������𐄐i����B
�ʌ����甭�����鉘�����ׂ̍팸���s�����߁A���o���镉�ׂ����邾���łȂ��A��
���A�Z���{�݂̐ݒu���ɂ��J���̗��o��}�����A�������ׂ̍팸��}��B
�i�ϓ��̊ϓ_����s�����V���ݓ��̉���ɂ��ẮA���I��݂̂̂łȂ��A����ɏZ��
�Z���̋��͂��d�v�ł���A�s�������̎�g�𑣐i����K�v������B
�s�s�̍ĊJ�����ƘA�g��̉������������ח��o�팸�{�݂̐������A�����p�ɂ₳����
�s�s�\���̍\�z��i�߂�B
�A �e�A�s�[���|�C���g�̐������P�̂��߂̎{��
�����p�S�̂̐������P�̂��߁A�e�A�s�[���|�C���g�ɂ����ė����Ƃ��Ď��{�����
�\�I�Ȏ{��͈ȉ��̂Ƃ���ł���B
�i�C�j ���Ȃ��̕l�`�����̕l����
��t�s�암�Z���^�[�ɂ����āA���x���������A�������팸��}����̂Ƃ���B
�܂��A��t�s����������ɂ����ẮA�f�����̃X�N���[���ݒu�A�����E�Z���{�ݓ��A����
���������̉��P��}��B����ɁA���n��ɗ�������͐여��ɂ����āA�P�Ə�������
�獇���������ւ̓]�����i�A���x�����^���̐ݒu���̐��i��}��B
�i���j �O�Ԑ�����
�]�ː썶�ݗ���]�ː���I��������ɂ����č��x���������A�������팸��}
����̂Ƃ���B�܂��A���n��ɗ�������͐여��ɂ����āA�P�Ə��������獇������
���ւ̓]�����i�A���x�����^���A�͐�̒��ڏ{�݂̐ݒu���̐��i��}��B
�i�n�j �����C�l��������
��ʌ��r�여��r�쏈���Z���^�[�ɍ��x���������A�������팸��}����̂Ƃ���B
����ɁA�����쓙���n��ɗ�������͐�ɂ����ğ��֓��̉͐��A�r��͌����
�����銱���̍Đ������{����B
�i�j�j ��������
�O�͓�������ō��x���������A�������팸��}����̂Ƃ���B�܂��A�����C�l
�����ւ̔��F�Ō`���̕Y������������[���Ƃ��邽�߁A�ʼnY������̏a�J��A�Ð여
��ɂ����ĉ͐쎖�ƂƉ��������ƂƂ��A�g�����J�������ǂ̐ݒu�A�J���f�����ɂ�����
�X�N���[���{�݂̐ݒu�����s���B����ɁA���c�여��ɂ����āA���ւ�͐�̒��ڏ{
�݂̐ݒu���ɂ�艘�����חʂ̍팸��}��B
�i�z�j ������͌�����
���s���X�͐������Z���^�[�ō��x���������A�������팸��}����̂Ƃ���B��
���A���]�菈����ɂ����ă|���v�꒾���r�̃h���C�����A�J���f�����ɂ�����X�N���[���{
�݂̐ݒu�����s���������������̉��P��}��B����ɁA�������������O�̗ՊC���ɂ�
���ẮA�P�Ə��������獇���������ւ̓]�����i��}��B
�i�w�j �݂ȂƂ݂炢�Q�P����
���l�s�_�ސ쉺��������ɂ����鍂�x�����̎{�ݐ����𐄐i����ƂƂ��ɁA�J���ؐ�
�r�ɂ�鍇�����������̉��P�ɂ��A�������ׂ̍팸��}����̂Ƃ���B
�i�g�j �C�̌����E���i������
���l�s����������ɍ��x���������A�������팸��}��ƂƂ��ɁA����|���v
�꒾���r�̃h���C����A�|���v��������̏��ł��s���B
�i���j�|���v�꒾���r�̃h���C���F�~�J�I����Ƀ|���v��ɂ����钾���r���ʼn���������
�܂��ؗ�������菜�����ƁB |
|
|