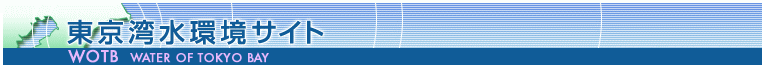|
東京湾は広義には三浦半島の剣崎と房総半島の洲崎を結ぶ線より北側の海域を指すが、狭義には、観音崎と富津岬を結ぶ線より北側を指す(以後「内湾」と言う)。
東京湾流域(ここでの東京湾流域は、水質汚濁防止法4条の2で定義された地域とする。以下、同様)は、南関東地域に属し、行政区域では東京都と埼玉県の大部分、神奈川県と千葉県の一部からなっている。これら1都3県は東京を中心とする首都圏を構成しており、我が国の政治、経済、文化等あらゆる面での中心となっている。東京湾流域は、面積では全国土の2%に過ぎないが、人口、工業出荷額については両者とも全国の約20%を占めている。
歴史的に見ると、東京湾では江戸時代から、河川や運河の浚渫にあわせた土地の造成がなされてきた。また、明治時代から戦前にかけては、横浜、川崎を中心とする京浜地区で工業集積用地の確保を目的に埋立てがなされた。昭和30年以降、本格的な経済成長の中、埋立地を中心に石油コンビナートや製鉄所の立地が進み、東京湾の西岸だけでなく、京浜から京葉へと工業地帯が発展した。また、首都圏への一極集中が加速し、工業団地、発電所、下水処理場、廃棄物処分場など都市住民の生活を支える広大な土地が必要とされ、埋立地の造成がなされた。昭和40年代後半のオイルショックで一時的に成長は鈍化したものの、その後再び活況を呈し、東京湾の臨海部は、一貫して日本の経済成長と都市住民の生活を支えてきた。最近では、業務機能を中心とした拠点的な地域整備やレジャー・レクリエーション拠点の整備、人工海浜、海釣り施設などの親水空間の整備も進められている。
東京湾に面する26の臨海市区(神奈川県三浦市から千葉県富津市の市区、東京都は特別区、横浜市、川崎市、千葉市は区)の面積は約18.8万ha
である。このうち、明治以降1990年8月までに埋め立てられた土地は約2.4万ha である。1991年の事業所統計によるとこの26の臨海市区に約474万人が働き、約601万人が居住し、埋立地に約49万人が居住している。
br> 海域利用についてみると、東京湾は、船舶の航行、漁業生産、海洋性レクリエーション等、多様な利用がなされている。現在、東京湾内6港には、年間約35万隻の船舶が入港し、年5億トン以上の貨物を取り扱い、首都圏の産業や都市活動を世界と結びつけている。湾内では、1日約4600隻、大小様々な船舶が航行し、非常に錯綜した利用となっている。漁獲量は年間約6万トンで、昭和50年以降ほぼ横ばいであったが、平成元年以降減少傾向である。海洋性レクリエーションについては、マリンスポーツを中心に拡大傾向にある。東京湾においても、過去には水浴場、潮干狩場などが湾内に広く分布していた。しかし高度成長期には水質の悪化及び海岸周辺の産業用地としての利用などにより、人々が東京湾と親しむ機会が減少した。近年では、親水護岸、人工海浜の整備等により人々の海への回帰が進み、水質改善の必要性が改めて求められるようになってきている。
|
|
|