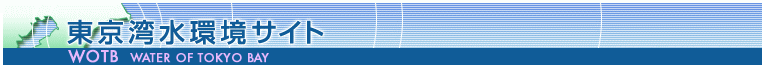|
東京湾を取り巻く環境は我が国の高度経済成長や首都圏
の発展とともに大きく変貌を遂げてきた。水質は昭和40年代に比べれば、改善が認められるものの、現在においても、赤潮、青潮の発生が繰り返され、また親水性の面や生物生息
の面からみてもその水質は決して良好な状況ではない。しかしながら、昨今、干潟や里山
など身近な自然に関する市民の意識が高まってきたこと、また、政府レベルでも、水質に関
して平成16年度を目標に汚濁物質の総量の削減目標等を定める総量削減基本方針が策
定されたこと、平成14年3月に新生物多様性国家戦略が関係閣僚会議決定されるなど、
官民を問わず、環境保全への取組みへの様々な動きが出てきている状況である。
このような中、本行動計画においては、都市再生という観点から都市住民にとっても、わ
かりやすい目標を定め、それに向かって関係行政機関を含めた関係者が連携協力して改善に取り組んでいくことが必要であると考え、次のような目標を掲げることとした。
〜 目 標 〜
|
【快適に水遊びができ、多くの生物が生息する、親しみやすく美しい「海」を取り戻し、
首都圏にふさわしい「東京湾」を創出する。】
|
具体的には、陸域からの汚濁負荷流入の着実な削減、海域での浄化対策などを通じて、
海の水質の改善を図るとともに、貧酸素水塊の発生を少なくし青潮の発生を抑制する等に
より、生態系を回復し、多くの生物が棲みやすい水環境となるよう環境の保全・再生・創造
を図っていく。これらによって、自然と共生した首都圏にふさわしい東京湾を目指す。
この目標が行動計画の実施によってどの程度達成されていくのかを具体的に判断する
ための指標として、従来の環境基準項目だけではなく、海域の富栄養化に密接に関連する
指標であり、かつ底生生物の生息に必要な底層のDO(溶存酸素量)に着目することが重
要である。そこで、海域全体に共通して「底層のDO」を指標とし、目標に対応する目安を
「年間を通して底生生物が生息できる限度」とした。
また、海域全体に共通した目安とは別に、個別の海域について、その特性に応じて指標
及び目安を定めた。
|
|
|