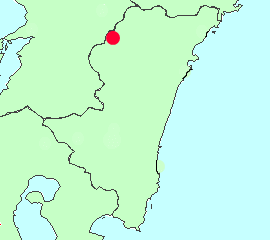


「妙見神水」は、祇園山の麓の妙見神社にある石灰岩の隙間から大量に湧出している。古くから「四億年の雫」「授乳の神水」と呼ばれ、生活用水として重宝された。本湧水を水源とした水田は「日本の棚田百選」にも選定されている。

湧水は、古くから鞍岡地区の上水道や農業用水に利用されており、近隣地域の生活用水としてかかせないものとなっている。特に、湧水を水源とした日蔭用水路の受益区域では水田を養う農業用水として活用されている。
|
 |

1日の湧水量:14,400トン

湧水の湧き出ている「妙見神社」は、貞観十一年(870年)清和天皇時代に建立、水神様として崇められ、その伝統を継承しており、古くから「授乳の神水」とも言われ、「妊婦が飲むと丈夫な子供が授かり母乳の少ない人が飲むと乳が良く出る」と伝えられている。

五ヶ瀬町日蔭土地改良区を中心とし、年間を通じた保全活動が行なわれており、湧水近辺の管理・清掃等は基より、用水路の水田使用期前の水路の清掃、近傍の自然を活かした「もみじ祭り」開催時の周辺整備等、地域住民が一体となり、日々保全活動に努めている。
|

