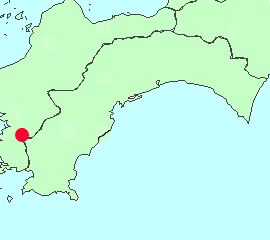


日本最後の清流「四万十川」中でも、特に「黒尊川流域」には美しい清流や、貴重な森林環境、今では数少なくなった農山村の風景など、自然の魅力が残っている。県により「人と自然が共生するモデル地区」に指定されている。

流域の飲料水の貴重な水源となっている。古くから稲作に利用されていたが、昭和52年からはアマゴ養殖も始まり、民宿など地域内外で利用されている。米ナス、ナバナなど園芸振興やゆず栽培にも利用されるなど、地域住民の生活になくてはならない水源となっている。以前は発電にも利用されていた。
|
 |

流域には幡州(土州)皿屋敷伝説が残るお菊の滝や黒尊神社、黒尊神社奥の院がある。黒尊神社に(神霊は大蛇といわれる)に願をかけ、「奥の院」に詣で、下の黒尊渕に願いを込めて生卵を投げ入れ、割れなければ願いがかなえられるという言い伝えがある。鎮守の森となる境内社前には根回り9m大杉があり、齢300年といわれている。

四万十くろそん会議を開催し、3グループを構成し様々な活動に取り組んでいる。例をあげると、水辺林の間伐、遊歩道の整備の実施、流域一斉清掃、地域の歴史・文化を伝承するため、播州皿屋敷のお菊伝説を紙芝居化し学校や老人クラブ等で活用などである。
|

