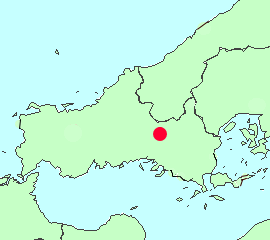


潮音洞は、錦川支流から用水を取り入れる隧道であり、県指定史跡となっている。漢陽寺本堂裏洞窟から流れ出る水は、境内の庭園を形成する水流となったのち、清流通り沿いへと流れ下流の用水として用いられる。

漢陽寺本堂西側の裏山に、潮音洞があることから、漢陽寺庭園(曲水庭:平安時代様式)は、潮音洞の水を利用し、禅庭とした珍しい曲水庭となっている。
約350年の間、農業用水として、また、防火用水としても活用されている。
|
 |

1日の湧水量:4,896トン

完成させた岩崎想左衛門重友の家系は、甲州の武田氏と関係があり、潮音洞を掘開した方法(水路の曲堀法、山の両側水位の測定法)は甲州流の軍法から発達したという節もある。
潮音の名は観音菩薩のように、慈雨を注いで民を潤すといった意味で、観音経普門品の「梵音海潮音、勝彼世間音」からとったものと言われている。

潮音洞の管理については、漢陽寺が維持管理を行っている。
水利組合が年2回(4月、9月)の溝普請を行っている。
清流通りについては、モニュメント広場、芝生広場、水草池、駐車場、便所、水路等の景観を守るため、清掃植栽管理・パトロールを実施している。
|

