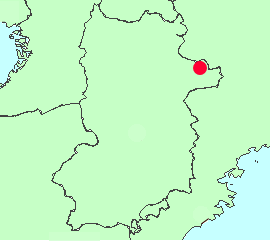


お亀池を中心として点在する「曽爾高原湧水群」には、サギスゲの群生地が確認されるなど、豊かな生物を育む源となっている。これらの自然を維持するための活動として行われる山焼きは、約千年の歴史があるといわれる。

本湧水は水量も多く、曽爾村大字太良路地内のほぼ全世帯及び全施設の生活用水として活用されている。また、昔よりこの湧水は、高原野菜の栽培・米作りなど農業振興についても利用されている。近年においては、曽爾高原の特産品として地ビールの醸造が行われている。
|
 |

1日の湧水量:約150トン

曽爾村はぬるべの郷といわれ、古くから良質なうるしが採れ、倭武皇子が曽爾村に漆部造(ヌルベノミヤツコ)を置いたのが、うるし塗りの始まりといわれている。本湧水が上質なうるしを育む源となっていたと考える。また、曽爾高原お亀池には大蛇伝説が残っており、大蛇が飲んだとされる場所は「水飲み」といわれ、現在も地域住民の取水場となっている。

曽爾高原及びお亀池の自然環境保全のため、年1回、行政と地元住民により曽爾高原の山焼きを実施。また、定期的なごみ清掃等を行っている。また湧水の保全用柵や保全シートなどによる保護を行っている。
|

