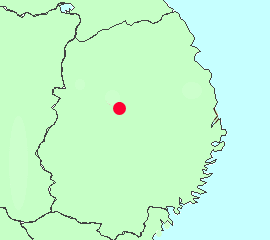


天保4年に記された「盛岡砂子」に記述があることから、これらの井戸は、江戸時代から地域の人々の生活を支えていたとされる。明治8年に組織された用水組合は現在も活動をつづけており、伝統的なルールが守られている。

吐水井から順に一番井戸は飲み水、二番井戸は米磨ぎ水、三番井戸は洗い物、四番井戸は足洗いと井戸の用途が定まっており、多くの人が安心して使うことができるように水利用のルールがある。
|
 |

1日の湧水量:67トン

両清水は江戸時代より重宝されてきたが、「青龍水」については天保4年、星川正甫が「盛岡砂子」(もりおかまさご)の中で「夏日は至って冷泉にて、厳冬温かなること湯のごとし。この辺はこの水によって居を保つ」という記述もある。

用水組合による清掃活動と維持修繕活動。現在は、毎週1回、井戸内及び井戸周辺の清掃をおこなっている。
|

