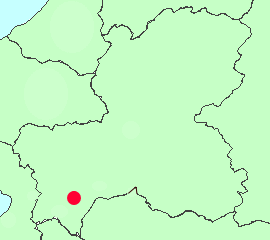


大垣市は豊かな地下水に恵まれ、古くから水都と呼ばれており、その代名詞である加賀野八幡神社の井戸舟からこんこんと湧き出る自噴水は、その光景と水質の良さ、おいしさから県内外からも水汲みに訪れる人が後を絶たない。

広く料理や飲用に用いられている。また、この地域では、水を大切に利用する工夫として、井戸舟という槽を何段か設け、上から順に飲用、野菜洗い用などに区別して使用しているが、槽の下流にハリヨの保護用の池を設け、その下流にカワニナ養殖とホタル保護の水路を設置しており、水のきれいさに合わせた活用をしている。
|
 |

1日の湧水量:430トン

加賀野八幡神社は文保元年(1317年)から10代、244年の長きにわたって続いた名門後藤家の居城、加賀野城の跡地の一部に建っており、古くは世安の荘の惣社で安産の神と伝えられている。

加賀野名水保存会では毎月2回の清掃やハリヨ保護網の設置、安全柵の設置、他地域のハリヨとの入れ替えの他に近年はホタルの幼虫育成やカワニナの養殖、排水管理なども実施、また不定期に子ども会との座談会及び清掃。他の市内環境団体との連携、各ネットワークへの参加。
行政と事業者が発足させた団体により、揚水の自主規制を開始。
|

