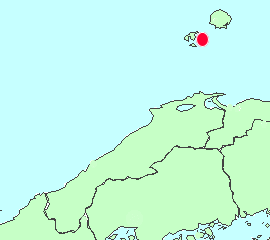


4月から9月にかけて周辺の木々の緑に覆われたり、目の前の田園風景と併せて情緒がある。

県指定文化財である観音像を有する清水寺境内にあり、水は境内の池に注ぎその周りは木々で囲まれている。また、道路を挟んだ目の前には田園風景が広がる。

10年前までは簡易水道水源として利用されていたが、現在は主に農業用水として利用されている。
|
 |

現在は簡易水道として使われていないが水量は選定時と変わらず400トン/日ほどと思われる。

奈良天平のころ僧行基が隠岐行脚で当地を訪れたとき、うっそうとした木陰の洞窟から流れ出る湧き水に霊気を感じ、ここに建物を建てて聖観世音菩薩をまつり、清水寺と号し、この水を天川(天恵の水)と名付けた。そのころからこの地方では湧水井戸を川と呼び、いつのころからか池をつくり石仏がまつられている。

清水寺境内の聖域として地元住民により大切に保全されている。
|

