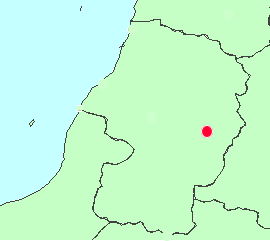


周辺の地域は、乱川扇状地の末端に位置する大富・羽入地区の湧水地帯。水源は東にそびえる御所山や黒伏山など奥羽山系の伏流水と考えられており、湧水池「地蔵沼」から湧き出る豊富な水は、清流小見川の源流となっている。小見川の上流域は県の天然記念物に指定され、湧水地帯だけに生息し「巣づくり」をするめずらしい魚、トゲウオ科トミヨ属「イバラトミヨ」が生息している。「イバラトミヨ」は、3月から7月頃に水中の草茎や毛根などに巣を作り、産卵・哺育する習性を持つ4〜6センチの淡水魚。氷河期からの遺存種と言われ、環境省で指定する絶滅危惧種である。また、小見川には、清流に住む魚の生活や、水の流れ浮き草等の自然環境を観察することができるように、水中が覗ける観察小屋を設置している。

小見川源流「地蔵沼」から流れ出す、冷たく澄んだきれいな水は、灌漑用水や鱒の養殖に利用されている。小見川で養殖された美味しい鱒は、東根市の特産品となっている。

サクランボの最盛期となる6月中旬には、さくらんぼの種とばし全国大会が開催され、さくらんぼを使ったユニークな競技に、各地から多くの参加者が押し寄せる。また、毎年トップアスリートをゲストに招き開催される「さくらんぼマラソン大会」には、全国から約5,000人以上が参加し、初夏の果樹園地帯を駆け抜ける。8月中旬には、本市の伝統的な祭り「ひがしね祭り」が盛大におこなわれ、期間中は県内外から約7万人の観光客が訪れる。
|
 |

水質・水量は、選定当時とほぼ変わらず良好な状態を保っており、「地蔵沼」から湧き出す、毎時約2,000トンの豊富で冷たくきれいな湧水は、「イバラトミヨ」の生息に最適な環境となっている。

大富・羽入地区周辺の地域は、昔からきれいな井戸水、どんこ水(どっこ水)で知られ、以前は、土地を10センチも掘ればすぐ水が湧き出したと言う。どんこの由来は、戦前、各家庭でこの湧水を生活用水に利用しようと、地区民が集まり井戸を掘ったときの掛け声が「どっこいしょ」「どんこいしょ」となまったもの、と言われている。また、仏具のひとつである「独鈷(どっこ)」に似た井戸掘り道具を使用して湧き出した水であることから、「どっこ水」になった、と言う説もある。最近は、水位が低下したため「どんこ水」のある家は減っているが、いまでも「どんこ水」が勢いよく自噴する井戸が残っている。小見川の源流である「地蔵沼」の由来は、奈良時代に大仏建立に尽力した僧行基が、この地を訪れ手作りの地蔵尊を残し、お堂に安置したが、後になってこの地蔵尊が沼に沈み「永遠に沼の水が絶えることがない」と村人たちに告げたと言われている。以来、「地蔵沼」周辺の自然環境は、地区民から大切に守られている。なお、小見川の豊富な水量と冷たい清流を利用し、東北で最初の鱒の養殖を手がけた場所と言われている。

地元住民は、「この素晴らしい自然の恵みを我らの代で枯らしては先祖に申し訳ない。孫の代に向けて大切に残そう」とその保存に取り組んでいる。湧水地帯をはじめ、「イバラトミヨ」が営巣している付近には側溝を設け、雨水や汚濁水が混入しないように清流保存の配慮がなされているほか、「大富イバラトミヨを守る会」による定期的な清掃活動や生息調査及び講演会をおこない、積極的な保全活動を行っている。
|

